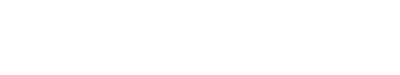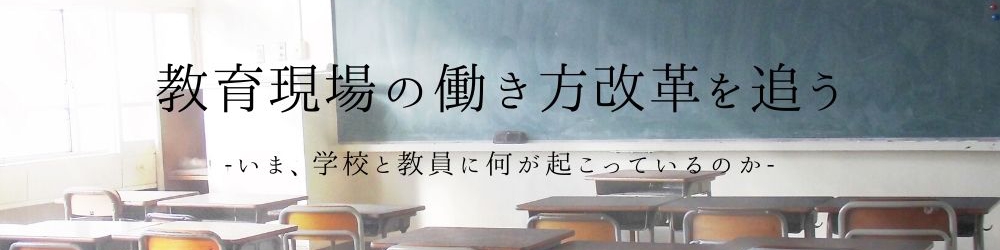疲弊する教員の「無関心」と、それを利用する者たち
【第6回】学校と教員に何が起こっているのか -教育現場の働き方改革を追う-
■日教組に起きた変化とは?
ただ、日教組側にも変化もあった。
「二本立て要求」と呼ばれることになるもので、ひとつは「教育労働の特殊性にかんがみ」ということで「定率(4〜8%)の特別手当(調整額を含む)を要求」している。
もうひとつは、自民党の労基法の「超勤事項は適用除外」に対して、クラブ活動や授業以外の指導など「測定可能な時間外労働」については、「労基法第37条に基づく割増賃金を要求する」というものだった。
前者では、定率特別手当を得ることで「教育労働の特殊性」を受け入れたことになる。「特殊性」は「無定量勤務の強要」につながる可能性をもっており、そのため、日教組内部からの反対は強かった。実際、この「二本立て要求」を日教組執行部が提案した日教組第82回中央委員会では、反対派が実力で委員会会場を占拠するという事態まで起きている。
後者の「測定可能な時間外労働」への労基法適用は自民党・文部省側からの強い抵抗があって揉めるが、時間外勤務を命じることができる場合を『生徒の実習、学校行事、職員会議、非常災害・児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合に限る』とする、いわゆる「超勤4項目」として給特法に盛り込まれていくことになる。
内部から大きな抵抗があったにもかかわらず、日教組執行部は「二本立て要求」で押し切る。そして、1971年5月24日、国会で給特法は成立した。
■当時と現在における「4%」の違い
超過勤務(残業)への労基法適用を原則にして「無定量勤務」に反対していたはずの日教組執行部は、なぜ「二本立て要求」に転じて、今日の「定額働かせ放題」への道を許すことになってしまったのか。その背景について「論文」は、以下のように指摘している。
「日教組内部にも調整額を受け取ることを良しとする声も確かに存在しているという状況認識と、超過勤務の排除と根本的な労働時間の短縮を理想とするにしても、近日中に政府・自民党からの法案が提出されようとしている状況においては、執行部原案こそが日教組全体をまとめることのできるものである、という見通しが執行部にあったことが推察される」
無定量勤務、つまり「定額働かせ放題」につながる危機感がある一方で、「調整額」を受け取ることの魅力にも惹かれていたというわけだ。もっとも、調整額の4%は当時の残業時間からすれば妥当だったとも言える事情もある。
しかし、当時にくらべれば現在の教員たちの残業時間は10倍以上にもなっている。にもかかわらず、調整額は4%のままで、「定額働かせ放題」となっている。
■教員たちの関心が鍵となる
この危険を予測しながらも、それを、より広い教員で共有できなかったことが、「定額働かせ放題」を生んだとも言えそうだ。
なぜ共有できなかったといえば、給特法が話題になり、日教組の幹部は大騒ぎしていても、大半の教員は「無関心」だったからではないだろうか。
そういった教員の姿勢は、冒頭で紹介した今回の給特法改正議論に対する教員の言葉に象徴されるように、実は今も変わっていないと感じる。
そして、10倍以上にも膨れあがるような残業を押しつけてきた文科省をはじめとする教育管理側は、そうした「教員の無関心」につけこんだのだ。
今回の給特法の改正も、教員の働き方の改善どころか、逆の方向につながりかねない危険性が指摘されてもいる。危険な方向に向かわせないために、教員が自らの「無関心」を変えていけるかどうか。
教育現場における働き方改革、いわば「教員の未来」はそこにかかっているのかもしれない。
- 1
- 2